「人類初の産業公害」と呼ばれることもある水俣病。石牟礼道子『苦海浄土(第一部)』(1969年)は、特殊な方法で水俣に生きる人びとの言葉を紡ぎ出す。この作品は、いかにして悲惨な現実を表象することができたのか? 私たちに遺された貴重な作品から〈方法〉を考察する、短期集中連載の第二回。
Written by 黒岩漠&井沼香保里
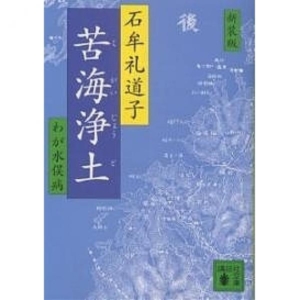
没入
1971年12月、グラフ雑誌『ライフ(Life)』などで活躍したアメリカの写真家、ユージン・スミスによって撮られた一枚の写真が発表された。「入浴する智子と母」(『ライフ』1972年6月2日号掲載)と題されたその写真では、有機水銀に侵され、口がきけず、四肢も目も不自由な「智子」を、湯のなかで「母」が抱きかかえるようにして洗っている。このモノクロ写真は、水俣病を世界的に知られるものにした作品であると言ってよく、またスミスの作品のなかでも最も知られた一枚である。
だが、最近まで、スミスと妻アイリーン・美緒子・スミスの写真著作権を管理する団体「アイリーン・アーカイブ」は、この水俣病のイコンにすらなった写真に、この先、一切の使用許諾を出さないことを決めていた。1996年、東京で開催されていた水俣病写真展、水俣から遠く離れた雨降る品川で、その写真が使われたチラシや濡れて剥がれたポスターが、駅から続く路上のそこら中に落ちている。都市の歩行者たちが、それを踏みつけながら歩いて日々の喧騒を稼働させている。その光景の耐えがたさが、遺族と団体にこの写真の封印を考えさせたという話だ(アイリーン・スミスのこの写真についての思いについては、以下の参考リンクを参照)。この一連の過程が、イコンとなった写真そのものよりも象徴しているだろう事柄に、思いを致さずにはいられない。
だが、いまはスミスの写真が抱え持つ、ある種の方法論へと視点を戻そう。それこそがこの写真をイコニックなものへとしたからである。というのも、この写真に写る二人の構図は、キリスト教文化圏においてはすぐに「ピエタ」〔十字架にかけられて死んだキリストを抱く聖母マリアの像〕を連想させるものなのであった。「ピエタ」と水俣の母子を構図において重ねる――この方法が写真を、そして水俣病を西欧において知られるものにしたと言ってよいだろう。この写真がアイコンよりも、むしろ〈イコン〉であるというのはこのためだ。要するに、スミスの作品に内在する方法は、水俣病患者の現実をキリスト教的文脈へと接続することで、イメージに西洋圏に広がる流通路を与えるものだったのだ。
それと比較したとき、石牟礼道子の『苦海浄土』における方法は、それとは真逆の地点に置くことができる(以下、石牟礼道子『苦海浄土 わが水俣病(新装版)』講談社文庫、2004年からの引用は頁番号のみを記す)。それは、対象を外在的イメージと重ねるのではなく、対象の内部へとひたすらに、ひたすらに沈潜していき、その深奥に棲みつくものをイメージとして引き上げる。対象そのものに語らしめようという強い志向が、たとえば土地の口語による表現――そこに表現される〈悲惨〉や、そこからの「かつての世界」への追悼的想起へとかたちを成していく。この志向は、たとえば次のような文章に表れている石牟礼の断言、いや、秘かな宣言をも導くこととなる。
死につつある鹿児島県米ノ津の漁師釜鶴松にとって、彼のいま脱落しつつある小脳顆粒細胞にとってかわりつつあるアルキル水銀が、その構造がCH3-Hg-S-CH3であるにしても、CH3-Hg-S-Hg-CH3であるにしても、老漁夫釜鶴松にはあくまで不明である以上、彼をこのようにしてしまったものの正体が、見えなくなっているとはいえ、彼の前に現われねばならないのであった。そして、くだんの有機水銀とその他〝有機水銀説の側面的資料〟となったさまざまの有毒重金属類を、水俣湾内にこの時期もなお流し続けている新日窒水俣工場が彼の前に名乗り出ぬかぎり、病室の前を横ぎる健康者、第三者、つまり彼以外の、人間のはしくれに連なるもの、つまりわたくしも、告発をこめた彼のまなざしの前に立たねばならないのであった。
146-147。
ここで老漁夫の前に現れなければならないのは、無論、加害者である「新日窒水俣工場」であるが、とはいえ、ただ彼らが謝罪と償いに現れればよいというだけではない。そこには、もう一つの含意があるだろう。すなわち、この「奇病」が、いかなる科学的説明によってでもなく、この老漁夫自身の言葉の身振りにおいて捕捉されなければならないのである。石牟礼は対象へと没入することで、その内部で捕捉しようと動くまなざしそのものへと転じ、〈悲惨〉を再現前させてゆく。
呪術師
石牟礼における内在への志向はまた、患者たちの投げ出された〈悲惨〉から、チッソへの、あるいは世界への〈憎悪〉をも引き出すこととなる。本書には、その点に関する石牟礼のはっきりとした意志が書き留められている。その部分は、本書におけるいわば零度の一点をなす。
水俣病の死者たちの大部分が、紀元前二世紀末の漢の、まるで戚夫人が受けたと同じ経緯をたどって、いわれなき非業の死を遂げ、生きのこっているではないか。呂太后をもひとつの人格として人間の歴史が記録しているならば、僻村といえども、われわれの風土や、そこに生きる生命の根源に対して加えられた、そしてなお加えられつつある近代産業の所業はどのような人格としてとらえられねばならないか。独占資本のあくなき搾取のひとつの形態といえば、こと足りてしまうか知れぬが、私の故郷にいまだに立ち迷っている死霊や生霊の言葉を階級の言語と心得ている私は、私のアニミズムとプレアニミズムを調合して、近代への呪術師とならねばならぬ。
74-75。
ここで石牟礼は、科学的(マルクス主義的)説明ではなく、「階級の言語」としての「死霊や生霊の言葉」を召喚しようと決意している――それを担う自己を「近代への呪術師」と規定しながら。本書が患者たちの置かれた〈悲惨〉や〈孤絶〉、そして追悼的想起を介した「かつての生活世界」と並んで書き留める、もう一つの要素が、この「近代への呪術」、あるいは憎悪なのである。
ほんにほんに。ひとを呪わば穴二つじゃ。自分の穴とひとの墓穴と。うちは四つでん五つでんひとの後に穴掘るばい。わが穴もゆりが穴も。だれの穴でも掘ってやろうばい。ただの病気で、寿命で死ぬものならば、魂は仏さんの引きとってやらすというけれど、ユーキ水銀で溶けてしもうた魂ちゅうもんは、誰が引きとってくるるもんじゃろか。会社〔チッソ〕が引きとってくれたもんじゃろか?
273;〔〕内引用者。

魂までも溶かしてしまうという汚染(本連載《1》の言葉を使えば、自然を侵す破壊的歴史性)という、被害者家族の語りから出てくるイメージ。ここでは、それが呪いへと向く折り返し地点になっている。あるいは作中に挿入された、ある患者女性(本連載《1》で触れた入院女性)の、ついには夫にも見捨てられてしまった憎しみを唄った次のような言葉は、呪術師ないし霊媒師としての石牟礼の方法を端的に示しているだろう(文中の「差別語」は、作品の時代性を考慮してそのまま引用する)。
生まれた、ときから、気ちがい、で、ございました。
そうつぶやく。そしてばったりひっくりかえる。
ここは、奈落の底でござすばい、
墜ちてきてみろ、みんな。
墜ちてきるみゃ。
ひとりなりととんでみろ、ここまではとびきるみゃ。
ふん、正気どもが。
ペッと彼女は唾を吐く、天上へむけて。
なんとここはわたしひとりの奈落世界じゃ。
ああ、いまわたしは墜ちよるとばい、助けてくれい、だれか。
314-315。
墜ちて、墜ちて、助けようもないほど墜ちた先で獲得されるのが、「死霊や生霊の言葉」、石牟礼における「階級の言語」であるとすれば、追悼的に想起される在りし日の記憶も、近代ないし世界へと向けられた憎悪も、彼らが〈孤絶〉へと投げ出されてある「奈落世界」から響く、そのような声において具体的に認識されなければならない。『苦海浄土』が描く極限状況における剥き出しの生死は、この声を獲得することで、「苦海」と「浄土」という真逆の二つを結ぶのだ。
表象
かつてある批評家は、批評は作品の破壊であると書いた。またその同じ批評家は、批評は作品を完成させるものだとも書いた。だとすると、1972年に『苦海浄土』が文庫化された際、そこに付録された編集者・思想史家である渡辺京二による「解説 石牟礼道子の世界」は、作品が自らに纏おうとしていた印象に対する破壊であると同時に、それを起点に作品をより高次の生の領域へと運んだという意味で、優れて批評的であった。その作品と批評の貴重な関係は、それ以降も、石牟礼の仕事を半世紀に渡って支えた渡辺のあり方を連想させるかもしれない。その批評における、作品の生にとって決定的であった指摘とは、作品の方法についてのものである。渡辺は、本書はすべてではないにしろ、一部の患者・家族の独白部分などは聞きとりをもとに(それをいくらか修飾したかたちで)成立したという考えの誤りを指摘する。
以前は私はそうだと考えていた。ところがあることから私はおそるべき事実に気づいた。仮にE家としておくが、その家のことを書いた彼女の短文について私はいくつか質問をした。事実を知りたかったからであるが、例によってあいまいきわまる彼女の答をつきつめて行くと、そのE家の老婆は彼女が書いているような言葉を語っていないということが明らかになった。瞬間的にひらめいた疑惑は私をほとんど驚愕させた。「じゃあ、あなたは『苦海浄土』でも……」。すると彼女はいたずらを見つけられた女の子みたいな顔になった。しかし、すぐにこう言った。「だって、あの人が心の中で言っていることを文字にすると、ああなるんだもの」。
370-371。
この作品は、患者たちの語りを、時間をかけて丁寧に聞き書きしたものをもとにしているわけでもなければ、患者家族の家に足繁く通って練り上げられたものでもなかったのだ。石牟礼は、「だって、あの人が心の中で言っていることを文字にすると、ああなるんだもの」という奇妙なほど確固とした自信のもと、患者の発することのない言葉を、一般的に言って勝手に、代弁するというかたちでこの作品を生み出したのである。石牟礼が、本書に与えられた第一回大宅壮一ノンフィクション賞を辞退したのも、このような方法上の背景があったからであろう。

では、本書が内包する患者たちの〈悲惨〉の、あるいはかつての美しい海の記憶の、あの生々しいまでのディテールもまた、彼女の脳内にだけ存在したのか?――渡辺は、もちろんそうではないと答えて、あのような叙述を成立させたものとして、近代において見捨てられてきた「生きとし生けるものが照応し交感していた世界」(374)があったということ、そのような世界を、「共同的な感性の根」(376)として、患者たちとともに石牟礼も分かちあっていたこと、また、実はというとそれほど牧歌的でもなかった前近代的世界を、これほど美しく想起する「一個の幻想的詩人」(378)としての才覚をも彼女が有していたことを挙げている。だが、この点についての考察は次回に譲って、ここでは、患者たちやその家族の話すことのなかった内面を代弁するという、その奇妙な〈方法〉にこそ注目したい。そこには、決定的なかたちで、表象における暴力の問題が現れているだろう。
表象(representation:代弁、再現前)という概念ないし問題圏――物語や表現という言葉でも同じことだが――は、二〇世紀以降の時代を思考する際に避けがたい主題と見なされてきた。たとえばアウシュビッツの絶滅収容所の内部で、あるいは原爆の投下された広島、長崎のキノコ雲の真下で、人間たちが置かれた状況、〈悲惨〉というよりほかないこれらの状況が、表象不可能である、にもかかわらず、表象されなければならないものとして、表象を要請するのだ。
しかし、そこで死んでいった者たち、あるいは語るという能力までも失って帰ってきた者たちの経験を、どのようにして代弁することができるというのか?
水俣病という問題を前に、『苦海浄土』の作者は、この問いに一つのシンプルな解答を用意した。すなわち、表象してしまう、というのがそれだ。たとえ「共同的な感性の根」がより豊かな表象を許したとしても、そこにある暴力性――この語を使うことを避けてはならない――を見逃して本書を読むことはもはやできない。この暴力性こそが、本書の担おうとした使命の在処を示すからである。実際に、もしいかなる表象をも持ちえなかったとしたら、〈悲惨〉は、完全なる沈黙以外のどこへ向かえばいいのか? これまで、原理的に数えあげることもできないそのような事態が、どれほどあったことだろうか? 「表象不可能性」を云々するばかりで、社会科学や哲学が躊躇して踏みとどまるところを、石牟礼の表象は踏破していく。真正性を欲しがらないことによって、表象が勝ち得るもののなかには、〈悲惨〉な運命にあらがう力量も含まれている。そしてそれは、(本連載でいずれ明らかになるように)少なくとも石牟礼においては、虫や蛙の声、波や風の声さえ「表象可能」であるという、かつてはより強大であった言語の根源的な力に由来しているのである。
(続く)




