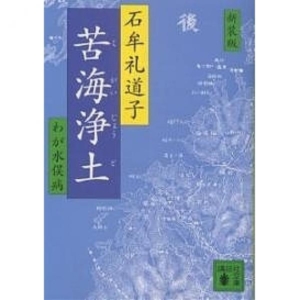奇天烈な姿で人々を魅了し続けるカンブリア紀の生物たち。本記事前半では、カンブリアの海に生きた生物の姿をほんの少しだけ紹介。また後半では、彼らをめぐる科学者たちの議論を検討しながら、私たち一人一人の存在の意味にまで考えを巡らせる。カンブリアの海から「多様性」を考え、そこから独特の歴史哲学へと思索を伸ばす奇抜な考察。
Written by 田中資太
動物の黎明、長い長い一日の夜明け
カンブリア紀の生物たち(以下カンブリアンクリーチャーズ=カンクリ)をあなたは目にしたことがあるだろうか?
23世紀の掃除機のような見た目のようなやつとか、放射線で魔改造された巨大クワガタのようなやつ…どれもこれもオーパーツ的で前衛芸術的で、最高にソソられるフォルムをしている。
「カンブリア紀」とは、約5億4100万年前から4億8500万年前まで続いた地球史における一時代である。それまでの生き物は大体がぺったんこで目も頭もどこかわからんような、生き物というよりウォーターベッドのような見てくれで、しかも顕微鏡でないと目に見えない程度のサイズのものばかり。それが突如「目覚め」、爆発的に多様化し、肩からスパイクを生やしてみたり、ムチのような触手をぶら下げてみたり、目玉を五つ生やしてみたり。いささかやり過ぎのファッション見本市のような状況を呈すのだ。
彼らの姿は僕らの存在とは遥かに隔たっているように見えるけれど、見方によっては僕らと近しい存在だともいえる。生物の誕生からカンクリの登場までおよそ30億年、それに比してカンクリから僕らの間には「わずか」5億年の道のりだ。ならば僕たち自身もまた、頭でっかちで毛がなくて指を五本も持った、カンブリアが生んだ珍妙な生き物だと言うことだってできるはずなのである。本記事ではごくごく一部ながら愛すべきカンクリたちの姿をご紹介しつつ、目線を反転させて、彼らから僕らがどのような哲学を引き出すことができるのか、思うところを書いてみたい。
カンブリアの代表選手たち
カンブリアの海にはどんなオモシロ生物がいたのか、ほんの少しだけ覗いてみよう。カンクリ関連書籍は豊富だし入手も容易だから、詳しく知りたい方はそうした書籍を手に取ってみてほしい。ここでは特に珍妙でよく知られた数種にだけ、ご登場願うことにしよう。
この時期最も繁栄していたのは、節足動物門に属す(と思われる)動物たちであった。その中に「オパビニア」がいる。

オパビニアは全長10センチ程度、身体の側面についたフラップを動かして、海中をウネウネ泳ぎながら食糧を探していた(よじよじ歩いていたという説もある。化石から生態を復元するというのは容易ではないのだ)。何といっても強烈なのは飛び出た眼を頭の上に5つもくっつけている所だろう。5つの視界はどのように世界を映していたのだろうか。頭の上にあるということは、プラネタリウムで星空を見上げるような具合に、海面を見上げながら泳いでいたのだろうか。
先端のノズルは一見獲物に向かって飛び出す口のようで『エイリアン』を思い起こさせる趣き。ところがこれ、自在に動かせるマジックハンドのようなもので、本当の口は頭の下に付いている。口の構造的にあまり硬いものや大きいものは食べられなかったらしい。
オパビニアの姿はあまりに奇天烈すぎて、初めて学会で復元図が報告された際には会場が笑いに包まれたというのは有名な話。カンクリの中でも特に見た目のインパクトが強い一種である。
それから、カンクリといえば「アノマロカリス」を一見しておかなければ嘘だろう。当時の最強生物の呼び声高い、恐竜で言うところのT・レックス的存在なのだ。

シュモクザメのような飛び出た目に、獲物を取っ捕まえるクワガタのようなハサミ。しかも大きいもので体長は40cmにもなる(かつては体長1mにもなると考えられていたが、最近はもう少し小さかったと考えられているようだ)。飛び出た目は柄の先に付いていて、上下左右に動かして広範囲に獲物をサーチすることができる。
口がまたものすごい。よく「パイナップルの輪切り」に例えられる、円形で二重構造になった口が、ぐわーっと開いて獲物にガブリと噛み付くのだ。実は最近の研究だと「あんまり嚙む力はなかったのでは…?」という意見も出ているようなのだが、カンブリアの海の王者として最も良く知られた存在であり続けている。
オパビニアやアノマロカリスら節足動物門は、前口動物に含まれる。一方で僕ら人間を含む脊椎動物門は後口動物に属している。僕らに繋がるカンクリはどんな姿をしていたのだろうか?
僕らの祖先の座をかつて欲しいままにしていたのは「ピカイア」であった。脊索を備えた、体長6センチほどの小さな生物だ。ところが新しい化石が中国で発見され、この時代すでに原始的な魚類が出現していたことが明らかになって、ピカイアは唯一の祖先候補の座から滑り落ちてしまった。

そして、もっと最近になって発見された最古の後口動物が「サッコリタス」だ。体長1ミリ程度、目はもっておらず、口は摂食と排泄の両方を行なっていた。

うーんこのフォルム。ピカイアはアニメに出演したが、コイツは無理そうだ。アノマロカリスたちの目を惹くフォルムを見た後だと、余計にパッとしない。ところがこうした生物から僕らは進化してきたというのだから、進化の道筋の不可思議さに思いを馳せたくもなるというものだ。
次は生物学者たちが、カンクリを通じて進化についてどのような議論をしてきたか、見てみることにしよう。
偶然と必然の間―カンクリをめぐって―
化石から復元されたカンクリたちは、何とも奇抜で奇天烈なフォルムで学者たちを驚かせた。その驚きは進化をどう見るかについての根幹について、さらには今生きている我々自身をどういう存在として見るかについて、丁々発止の議論を呼び起こしたのだった。
カンクリをネタに、進化についてのラディカルな考えを広く大衆向けに発表したのは、S.J.グールドの『ワンダフル・ライフ』(原著1989年;渡辺政隆訳『ワンダフル・ライフ バージェス頁岩と生物進化の物語』早川書房、2000年)だ。彼はカンクリの想像を超えたデザインのあれこれを目の当たりにして、この時代に生物の多様性は極大に達していたと考えた。そしてそこから「主として偶然によって」ある種は絶滅し、多様性が瘦せ細ってきたのが進化の歴史だと考えた。ホモ・サピエンスがこの世界を我が物顔で闊歩しているのも、単なる偶然の結果でしかないのだ、と。
こんな風に「偶然」の要素を最大級に重視することは、人間は進化の頂点にいるわけではないということを強調する一方で、「個」を最大限に尊重するものだろう。わたしが今ここに存在するのは数えきれないほどの偶然のおかげ、奇蹟の賜物なのだ、というわけだ。
グールドのラディカルで大衆受けする見方に対しては、実際にカンクリの研究に従事していた最高峰の研究者たちから至極もっともな反論があった。S.C.モリスは言う。たしかにグールドのいう通り、ある特定の種、ある特定の個体が出現することを予測することなどできはしない。例えばもし君のパパとママが愛を交わしたのが別の日だったら、授かった子は君とは別の誰かだったろう。
でも、その存在したかもしれない「別の誰か」も、立派に君のパパとママの子としての役目を果たしただろう。それと同じように、例えば「鯨」という種が進化していなかったとしても、「海のなかを素早く泳ぎ、海水を濾過して食料を得る生き物」は存在していただろう。だから進化はグールドの言うように、偶然に支配されているとはいえない。それが進化の面白いところなのだ。そうモリスは説く。
モリスの言う通り、研究が進むにつれて、一見奇天烈なカンクリたちも進化の道筋から外れた迷い子たちではなくて、生物の分類図のどこかにきちんと収まっていたことが明らかになっていっている。また「光スイッチ説」のように、急激な多様化を説明する理論も登場してきた(眼を獲得した生物が捕食に有利となり、それによって進化のスピードに拍車がかけられたとする説)。彼らは決して、神の野放図な悪戯の賜物などではなかった。
けれども。僕らが思考を始めるのはここから。モリスの出した「私ではない別の誰か」という比喩は、果たして本当に適切なものだっただろうか?言い換えると、ある形式を備えた「種」が出現する可能性と、ある「個」が世界に生まれ落ちる可能性とは、同列に語ることができるのだろうか?今度は、今ここに立つ僕とあなたを、遥かカンブリアの海の波間に揺蕩っていた愛すべき生物たちの小さな眼に映して眺めてみよう。そうすることで、僕らにとって彼らが神様の気まぐれとも見えるのと同じように、僕ら自身の存在もまた、可能性という無数に枝分かれする灰色の系譜の枝先に、煌々と光る一つの灯火として見えてくる。
5つの眼に映った私
カンブリア紀の暖かく浅い海の中、生物を満載した闘技場の壁のように聳える海底崖の麓に、僕とあなたが滑り降りたとしたら。僕らの姿はオパビニアの5つの眼に、どのように映るだろうか。
僕らの腕は、長く伸びて五つ股に分かれた触手のように見えるだろうか。自分が付けているノズルに比べると、大して自由には動かなそうだ、そう思うかもしれない。あんなにつるつるした胴体ではさぞ泳ぎにくいだろう、そんな憐憫の気持ちを抱きながら、自分のフラップを優雅に動かして、僕らを尻目に素早く去っていくのかもしれない。
アノマロカリスは僕らの口を見てどう思うだろう。あんな風に上下にしか開かないようでは、目の前にいる獲物に齧りつくにも苦労しそうだな。しかし口の奥から飛び出すあのピンクの平べったいものは何だろう。獲物を捕らえるにしては短いし、気味が悪いな。円い口の中の食べ物をじっくりと噛みながら、そんなことを考えるかもしれない。
こうして少し想像を広げてみるだけで、カンクリの奇天烈さというのはそのまま、僕たち自身の奇天烈さとして跳ね返ってくる。相違は常に相対的なものでしかなく、ある立場からの見方を内に孕んでいる。カンブリアの眼差しを借りて相違を捉えたときには、白人と黒人の、中国人とブラジル人の、僕とあなたという「個」の間に横たわる相違など、さして重要ではないともいえる。その誰もが5つ股の触手を2本生やした、カンブリアの奇妙な末裔なのだ、と(この点では下のスターウォーズ記事もテーマが近い)。


とはいえ、モリスの比喩はあくまでも「種」の進化に関わる次元の問題であって、人間の歴史や行為の次元での問題とは区別しておかなければならない。確かに、ほんの一歩、わずかな風の流れの違いで、僕は僕でなかったかもしれず、そしてそれでも世界は素知らぬ顔をして回っていたかもしれない。しかしそんな風に、自分あるいは他者を、単に種のなかの一個体として割り切ってしまうことには、非常な危険がつきまとう。
一つには、責任の問題がある。もし、僕と別の人間が単に交換可能な存在だとしたら。ヒトラーやポル・ポトが生まれていなくとも、どうせ別の人間がその役割を果たしていただろうと考えるとしたら。それはつまり、人間の行為は単に状況から弾き出されるアウトプットにすぎないと考えるということだ。そうなれば、犯された罪を償う者もなく、罪への赦しもまた存在しないことになる。モリスもこの点には触れていて、種の歴史からは人間の悪業の歴史は説明されえないのだと、そう著書の末尾に書きつけている。
しかしもう一つ、モリスが触れていない問題がある。責任の問題が過去へ向かう人間的な態度だとすれば、それと対になるのは、未来に対峙する上での人間的な態度、未来へ向かって行う約束だろう。他者に対して、あるいは自分に対して交わす約束は、有りうるいくつもの可能性の中から、ある一つを自分の手で選び取っていく瞬間だ。その積み重ねは、状況それ自体を変えていく力をも持ちうる。そして他ならぬ僕やあなたがどんな約束をするかは、「個」としての僕やあなたの存在にかかっているのだ。
さて、最後にもう一度、「個」としての僕たちから、カンクリたちを眼差してみよう。彼らはもはや、自分たちで未来を選び取っていくことはない、いや、最初から彼らにはそれが許されていなかった。オパビニアの中にも、自分のノズルの短さに悩む奴なんかがいたかもしれないが、それをどうすることもできなかっただろうし、どのみち僕らには知りようがない。僕らは頁岩に刻印されたカンクリたちに思いを馳せながら、種の一員として歴史に拘束された自分と、個として無数の可能性を秘めた自分との間で、良い具合に折り合いをつけていくのだ。