「人類初の産業公害」と呼ばれることもある水俣病。それを描いた『苦海浄土』の方法は、石牟礼道子自身の性質とどのように関わるのだろうか? しばしば幻想的とされる石牟礼の水俣をめぐる文学は、いかに現実と結びつくのだろうか? 現実と幻想という大きな二元論を架橋する石牟礼の表現の根にある〈なにか〉に迫る、短期集中連載の第4回。
Written by 井沼香保里&黒岩漠
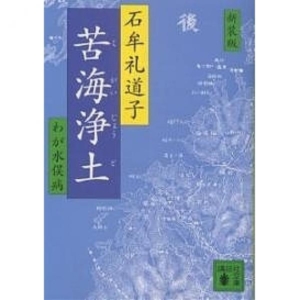
幻想性
多くの批評家や文学者が指摘するように、『苦海浄土』は、たんに苦しみを苦しみのまま提示したり、それを告発したりしようとするのではなく、苦しみを超えた幻想的世界を、美しい古代への憧憬を物語っている。
石牟礼の追悼として組まれた2018年5月の『現代思想』総特集のなかで、社会学者の栗原彬も、歴史学者の藤原辰史との対談のなかで次のように述べている。
しかし、石牟礼さんは苦しみや呻きを聴いていただけではありません。それだけでは、「耳を澄ます」ことにしかならないのです。だからその先がある。あの者たちの声を聴いて聴いて、聴きぬいた先に、美しい実を見つけている。石牟礼さんの作品のなかには、いつも苦しみがあります。(中略)しかし、その苦しみをむき出しのまま語るのではなく、変えているのです。そこで美しいものが出てくる。『苦海浄土』であれば「ゆき女聞き書」です。(中略)しかしその美しさは、奈落の底に落ちていく苦しみや嘆きを聴いていたからこそ生まれたものでした。そうしたものを通り抜けてきたために、幻想的な美しい世界を生み出さざるをえなかったのです。
栗原彬・藤原辰史「化生の音を聴く」『現代思想』5月臨時増刊号、青土社、2018年、75。
患者たちの痛苦を腸にまで落とし込み、自らの言葉、抑揚、リズムで表される石牟礼の筆致は、読者を、苦しみに満ちた現実とは異なる地平、幻想的な「もう一つのこの世」に誘うのである。
では、現実の痛苦を味わい切った先に生まれるこの幻想性は、現実への反動として捉えるべきなのだろうか。渡辺京二が、「『苦海浄土』を統一する視点は(中略)、この世界からどうしても意識が反りかえってしまう幻視者の眼」だといい、「ゆき女聞き書」や「天の魚」における海上生活の描写の「美しさは、けっして現実そのものの美しさではなく、現実から拒まれた人間が必然的に幻想せざるをえぬ美しさにほかならない」(渡辺京二「解説 石牟礼道子の世界」『新装版 苦海浄土 わが水俣病』、2004年、384-385)というとき、そこには現実と幻想が二律背反的に設定されているように思える。
しかし、本連載《2》や《3》でみたように、石牟礼が『苦海浄土』を書く自分自身を「呪術師」や「族母」に位置づけようとするとき、彼女は近代世界とそこから孤絶した世界の、主婦と物書きの、媒介者たらんとしていた。だとすると、現実と幻想という二つの異なる領域もまた、彼女をして媒介されるのではないだろうか。
浮遊
『苦海浄土』と並んで「もう一つのこの世」を徹底的に再現した作品である、『あやとりの記』(1980~82年連載)は、水俣の在りし日の情景を石牟礼自身の幼少期の回想という体裁で書かれている。いわば、『苦海浄土』で描き出された幻想性が、より前景化した作品であるといえるだろう。この著書の次の一節が、上述の媒介がいかになされるかを考える際の起点となるのではないか?
草履を両方とも川の水にあげたのは、もうずうっと大昔の、生まれないぐらい前から、水に呼ばれているせいかもしれません。
水連の葉っぱの露の玉や、小川の岸の草の葉先で、今にもこぼれ落ちそうになっている露の玉を見かけると、息が止まるかと思うほど、胸がどきんとすることがありました。
(生まれる前のわたしかもしれん!)
と思ってしまうからです。生まれる前の自分、ああなんとその自分に逢いたいことか。みっちんが、水とか露とかを見て魂がとろとろなるのは、そういうわけなのです。
石牟礼道子『あやとりの記』福音館書店、2009年、241。
目の前の葉っぱの露の玉は、気象条件や草木の茂り具合によって束の間、偶然に現れるにすぎない。主人公かつ筆者のみっちんは、その偶然性をまとった清らかな雫に、「生まれる前のわたし」という、すでにそこにはないもの、あったかどうかも定かでないもの、幻とでもいえるものを見出して重ね合わせようとする。

露の玉という偶然性と、生まれる前のわたしという幻想性、そして「かもしれない」可能性が折り合わさったこの描写は、もはや幻想という一言で片づけることができないような独特な感覚を与えているように思われる。つまり、読者を、現実から勢いよく引きはがして幻想的な世界へと投げ込んでいるというよりは、彼らを依って立つ足場からふわりと解き放ち、四方八方へ漂うことを可能にしながらも、ついにどこにも位置づかせることのないような、そうした浮遊の感覚とでも呼べるものを与えているのだ。
ではこの浮遊の感覚は、物語世界においてのみ可能なものなのだろうか。ここで少し視点をずらして、同じく水俣病によってもたらされた怒りや苦しみを生き抜いた緒方正人の語りを参照してみよう。なぜなら上記の浮遊感に共振するものが、緒方の「狂う」という体験のなかにも見いだすことができるからだ。
狂い
緒方は水俣病で最愛の父を失い、この怒りを腹の底に抱えながら大人になり、水俣闘争を牽引する一人となった。しかし、金銭的解決を望む患者や運動家たちの主張に対して、彼は金銭ではなく、この問題を生じさせた社会構造そのものに異議を申し立てたため孤立する。それまで世話になった人たちに別れの挨拶をして、現実の人間関係から自らを切り離していく過程で、彼は自らが探しているものも見失い、何の支えも得られなくなり、〈狂う〉。自分を自分たらしめる足場や人とのつながりが失われ、いわば重度の鬱状態に陥ったのだ。

緒方の〈狂い〉が、他者との紐帯から切り離された結果、すなわち他者との関係性ないし差異のなかで自己を保持することができなくなった結果として生じたものであったのならば、前述の『あやとりの記』にみられる浮遊感もまた、他なるものを切り離すのではなく、それと一体化することによってではあれ、同じく差異が消失した状態に行きついている。
この非差異化の過程は、フロイトが『快感原則の彼岸』(1920)で、人間におけるもっとも原理的な欲望として提起した「死の欲動」という概念と重なり合う。文学研究者のローズマリー・ジャクスンは、サドの幻想的作品との親縁性を指摘するなかでこの概念を次のように説明する。
〔死の欲動は〕存在を止めたいという単純な欲望ではない。(中略)それは、あらゆる緊張が弛緩する場所、涅槃への憧れなのである。彼〔フロイト〕はこの状況をエントロピー状態と名付け、さらにエネルギーすなわち有機体が持つエロス的で攻撃的な欲望にエントロピーを対抗させる非差異化への欲望を、エントロピー的引力と名付けた。
ローズマリー・ジャクスン著、下楠昌哉訳『幻想と怪奇の英文学III――転覆の文学編』春風社、2018年、125-126;〔〕内引用者補足
つまり、死と、非差異化がもたらす〈狂い〉は、イコールの関係にある。実際、緒方は〈狂って〉いたとき、「死への誘いも一日中無数にあった」という(緒方正人語り、辻信一編著、『常世の舟を漕ぎて 熟成版』素敬 SOKEIパブリッシング、2020年、130)。〈狂い〉の果て、欲動される死を飼い馴らした緒方がたどり着いた「チッソは私であった」という思想は、批判の矛先としての近代を自己と一致させるという意味で、そうした非差異化の表明であったといえるだろう。
孤独
話を石牟礼に戻そう。『あやとりの記』にみられる浮遊感が、いま見てきたように〈狂い=死〉と親和的であるとするならば、ひょっとすると石牟礼自身も、こうした〈狂い=死〉と案外近い位置にあったのではないだろうか? 実際に、栗原が先述の対談で述べている、「〔石牟礼が〕『森の中に入って自殺しようと思っていた』と、事もなげに言われるのを聞いたことがあります」(栗原・藤原 73;〔〕内引用者補足)というエピソードには、石牟礼にとって死とはこの世の営みからかけ離れた畏れ多いものなどではなく、彼女が日常的に抱いていた感覚と連続的であった可能性を示唆している。
石牟礼が日常的に抱いていた感覚とは、緒方がそうであったように、〈孤独〉である。渡辺京二は、石牟礼が生涯にいくら人に好かれ、多くの人と繋がっていても、そこには決して埋められない孤独と不幸感があったと述べている。
とにかくあの人は面倒見てやらんといかんというふうに思わせるのが上手な人だったんだよ。作為的にやってということじゃないよ。自然になんだけどね。だから、あの人の周りには、この人には何かしてあげなきゃいけないと思っていた人がいっぱいいたんだよ。(中略)だけど、それが彼女の悪い癖になるとね、『私はこんなに苦しんでいる、私はこんなに孤独だ』みたいなことをね、酔っぱらって言うことがあってね。そう言うと、男連中が真に受けて『そんなにおつらいんですか』とか言うわけですよ。名のある男たちが。僕は『阿呆が、引っ掛かって』と思って見てましたけどね。僕は『文学者たるものが、そんなこと言うもんじゃない!』と思うわけね。
渡辺京二=語り、聞き手=アルテリ編集室「渡辺京二 2万字インタビュー」『アルテリ』七号、アルテリ編集室、2019年、28。
彼女の不幸感というのは、つまり世の中で迫害されたとか、いじめられたとかでなったんじゃないんだよ。生まれついてのこの世への違和感というかね。この世の欺瞞が嫌いで、とにかくハリネズミのような少女だったわけです。
同上、19。
彼女は、人との繋がりというものがまったく救いにならない次元で、孤独におかれている感覚があったのだ。

この孤独感が『苦海浄土』を生んだといっても、決して言い過ぎではないだろう。共同体の中で孤独であることは、「呪術師」や「族母」といった一種霊能がかった資質に適う要素であり、同時に〈孤絶〉へといたった水俣病患者らに対する鋭敏な眼差しや共感を抱く素質でもあるだろうから。
したがって、本稿の冒頭で問題化した現実と幻想の二つの領域は、孤独――あるいは〈狂い=死〉――によって媒介されるといえる。彼女の表現の核にある、森羅万象や過去との自由で軽やかなつながりが現出させる美しい幻想性は、他者には理解も感知もできないほどにこの世のあらゆるつながりが絶たれているからこそ、逆説的に、現実と何の矛盾もなく非差異的に連続したものとして立ち現れるのだ。
(続く)




