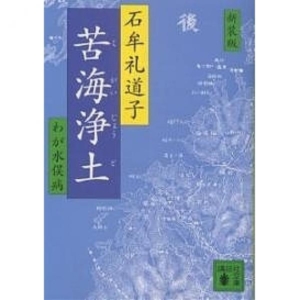民俗学者・宮本常一が、自伝『民俗学の旅』(1978年)のなかで語った父の言葉。それは、〈経験〉によって培われた貴重な教えであった。現在に生きる私たちは、それをどのように受け取ることができるのか? 宮本の父の言葉から〈経験〉の行方へと目を向ける、歴史的思考。
Written by 黒岩 漠
父の言葉
見る、きく、歩く、あるいはそうやって出会った人びとと、話す――こういった人間の基礎的と言うべき一つひとつの所作を、最も徹底的に行った研究者の一人として、宮本常一(1907-1981年)がいる。柳田國男、そして渋沢敬三に師事し、日本列島中を歩きまわって優れた民俗誌を残した。見る、きく、歩く、話す――その膨大な作業のなかで、宮本は、これらの所作を研ぎ澄ましていったのだ。その成果は、最もよく知られた作品集『忘れられた日本人』(岩波文庫、1984年;初版1960年)をはじめとする彼の著作のなかで確認するしかない(いずれそのような記事も出るだろう)。
ここで取りあげたいのは、その宮本の自伝『民俗学の旅』(講談社学術文庫、1993年;初版1978年)に記されている、郷里を離れるときに父に言われたという言葉である(以下、『民俗学の旅』からの引用は頁番号のみを記す)。
小学校を卒業したあと(1930年頃のことか)、父のもとで百姓として一年を過ごした彼は、親類のすすめで都会へと出ることになる。父も、「世の中へ素手で出ていくには身体がもと手であるから、どんな苦労にも堪えられるようにしておかねばならぬが、一年間百姓させてみてもう大丈夫だと思う。何をさせてみても一人前のことはできるだろう」(36)と述べて認めてくれた。そして宮本が家を出る際に、いろいろのことを教えてくれた。「私はこのことばにしたがって今日まで歩きつづけることになる」(38)――それは以下の10ヵ条としてまとめられているが、長くなるけれども、ここでそのすべてを引用しようと思う。何かそれ自体に対して解説のようなものを付ける必要などまるでない、素朴で、豊かな〈よく生きる〉ための言葉である(以下、36-38;ただし見やすくするために、項目ごとに一行ずつ空ける)。
(1)汽車へ乗ったら窓から外をよく見よ、田や畑に何が植えられているか、育ちがよいかわるいか、村の家が大きいか小さいか、瓦屋根か草葺きか、そういうこともよく見ることだ。 駅へついたら人の乗りおりに注意せよ、そしてどういう服装をしているかに気をつけよ。また、駅の荷置場にどういう荷がおかれているかをよく見よ。そういうことでその土地が富んでいるか貧しいか、よく働くところかそうでないかよくわかる。
(2)村でも町でも新しくたずねていったところはかならず高いところへ上ってみよ、そして方向を知り、目立つものを見よ。 峠の上で村を見おろすようなことがあったら、お宮の森やお寺や目につくものをまず見、家のあり方や田畑のあり方を見、 周囲の山々を見ておけ、そして山の上で目をひいたものがあったら、そこへはかならずいって見ることだ。高いところでよく見ておいたら道にまようようなことはほとんどない。
(3)金があったら、その土地の名物や料理はたべておくのがよい。その土地の暮らしの高さがわかるものだ。
(4)時間のゆとりがあったら、できるだけ歩いてみることだ。いろいろのことを教えられる。
(5)金というものはもうけるのはそんなにむずかしくない。しかし使うのがむずかしい。それだけは忘れぬように。
(6)私はおまえを思うように勉強させてやることができない。 だからおまえには何も注文しない。しかし身体は大切にせよ。 三十歳まではおまえを勘当したつもりでいる。しかし三十すぎたら親のあることを思い出せ。
(7)ただし病気になったり、自分で解決のつかないようなことがあったら、郷里へ戻ってこい、親はいつでも待っている。
(8)これからさきは子が親に孝行する時代ではない。親が子に孝行する時代だ。そうしないと世の中はよくならぬ。
(9)自分でよいと思ったことはやってみよ、それで失敗したからといって、親は責めはしない。
(10)人の見のこしたものを見るようにせよ。その中にいつも大事なものがあるはずだ。あせることはない。自分のえらんだ道をしっかり歩いていくことだ。
経験ということ
宮本常一の父は、貧しい百姓であり、満足に小学校にも行かせてもらえなかったのだという。しかし、そのようなことが知性の多寡を意味することなどないということを、いまさら述べる必要はないだろう。父が語った言葉は、大学で教わったり、本を読んだりするだけで身に着けたつもりになれるような、そのような類いの知性では全くない。これらの言葉から感じ取れるものは、むしろ膨大な時間の経過――彼が百姓として過ごしながら、自らの力で少しずつ考え、また改めては考え、という日々を寡黙に過ごしてきた、その時間の経過であろう。そうして育まれたものは、やはり〈経験〉としか呼びようのないものだ。子が家から旅立つとき、親が贈ってあげられるものとして、これ以上のものがあるのだろうか?
しかし、現在の地点からこのような〈経験〉の言葉を読むとき、僕らは自らの置かれたある種の事態をも認識することになる。それは、大学出のエリートでなくとも豊かな知性を獲得できる、などという一般受けもよい教訓などではない。むしろ学歴などというものの有無に関わらない、より深刻な危機的事態、すなわち〈経験〉を形成できていないという事態を認識せざるをえないのだ。実際にも僕らの時代に、宮本に父が贈ったような言葉とそう出会うことがあるだろうか?
実は、この、〈経験〉の貧困という危機は、20世紀の初頭から現在にいたるまで、多くの観察者によって繰り返し確認されてきたことである。かつてある思想家が述べたように、〈経験〉とは物事との相互的交渉であり、その結晶物としての態度や知恵をいうのだとしたら、現代はそれとは真逆のところへと舵を向け続けてきたのだ。
年長者であれば、若い世代に自らの〈経験〉を誇ってみたくなるものだ。ところが、実際にそのようなものを獲得できる余地は、この時代にはほとんど残されていない。あるとしても、それはたんなる「職業経験」――しかもそれですら、ほとんどの場合はわずかな年数で他人に代替されてしまう程度のものだ――に過ぎないか、「体験」と「習慣」の束がたんに〈経験〉と誤認されているに過ぎないか、といった具合である。〈経験〉を譲渡できるということが年長者の〈権威〉の根源であるとすれば、現在、年長者が若い世代に譲渡できるものとは、いくらかのインフラ以外には、放射能が漏れる壊れた原発や崩壊した社会保障制度、折り返し地点を見失った環境悪化問題、いまだ解決の見えない戦争責任問題…といった代物であって、それらは社会関係において最も重要な要素の一つである〈権威〉を、その根源において喪失させていく。
個別の〈経験〉が消失してしまった、というよりは、〈経験〉が事柄の生成核になっているような世界が失われた、と言っても同じことだ。その過程は、別の側面から見るのならば、新聞、テレビ、そして現在ではインターネットといったマス・メディアの登場と普及という歴史的文脈を持つ。マス・メディアによって媒介(media)されることで成立する人間集団が大衆(mass)であって、それは、民俗(folklore;民間伝承、民俗学)によって媒介されることで成り立つ民衆(folk)というあり方を駆逐するようにして台頭していった。いまから百年ほど前に柳田國男が日本列島で民俗学を構想したとき、それはすでに、現代において民俗が失われていくことへの危機感からであった。宮本が列島を歩いていた頃が、滅びかけている民俗、その最後の輝ける時期だったかもしれない。
では、その喪失の先に僕らはいかなる方針を持つべきなのか? 〈経験〉の貧困のなかをどのように〈よく生きて〉いけばよいのか? あるいは宮本の父の言葉を、どのように(あるいは変形して)読むべきか? それとも、あれらの言葉はもはや無用の長物なのか?――そのこと自体を、直感的なものを含め、〈経験的〉に判断しなくてよいということは、この際、幸いである。