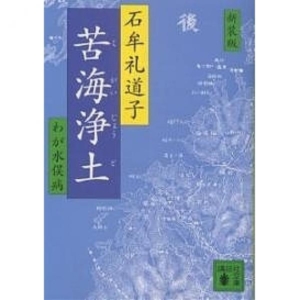「人類初の産業公害」と呼ばれることもある水俣病。石牟礼道子『苦海浄土(第一部)』(1969年)は、そこに生きる人びとの生死を艶やかに描き出す。私たちの時代は、なぜ再びこの作品を新鮮に受けとりなおす必要があるのか? この傑出した作品から現在を照らし返す、短期集中連載の第一回。
Written by 黒岩漠&井沼香保里
不知火
たとえば、かつて次のように語られた事態を、私たちはどのように受けとることができるだろうか? そのような事態を生み出した世界に対して、現在の時点で、どのような認識を持つことができるだろうか?(以下、石牟礼道子『苦海浄土 わが水俣病(新装版)』講談社文庫、2004年からの引用は頁番号のみを記す。)
おとろしか。おもいだそうごたなか。人間じゃなかごたる死に方したばい、さつきは。わたしはまる一ヵ月、ひとめも眠らんじゃったばい。九平と、さつきと、わたしと、誰が一番に死ぬじゃろかと思うとった。いちばん丈夫とおもうとったさつきがやられました。白浜の避病院に入れられて。あそこに入れられればすぐ先に火葬場はあるし、避病院から先はもう娑婆じゃなか。今日もまだ死んどらんのじゃろか。そげんおもいよった。上で、寝台の上にさつきがおります。ギリギリ舞うとですばい。寝台の上で。手と足で天ばつかんで。背中で舞いますと。これが自分が産んだ娘じゃろうかと思うようになりました。犬か猫の死にぎわのごたった。
46-47。
いわゆる水俣病という名とともに知られる一連の事態――すなわち、新日本窒素肥料株式会社(以下、チッソ)が不知火の海に多量に流したメチル水銀の蓄積によって、沿岸の漁民を中心として、魚を食べて生活していた人びとに「奇病」が発生したということを、私たちはすでに知っている。またチッソが、社内においてその因果関係を把握していたにもかかわらず、それを隠し、そればかりか大学での原因究明を妨害までして汚水を流し続け、一方の行政もまた長らくまともな対策を取ろうとしなかったということ。そのことによって、「人類初の産業公害」と呼ばれる事態はどこまでも拡大し、水俣病認定と被害補償をめぐる争いが現在まで続いていること。そして、これらのすべての過程において、被害者に対する差別が公然と語られたことも、一応は知識として持っているだろう(水俣病についての基礎的な知識は、以下の水俣病資料館のホームページでも知ることができる)。
だが、石牟礼道子『苦海浄土』(初版1969年)がここで描くものとは、そういった一連の過程というよりも、むしろそこでの〈悲惨〉そのものである。手軽な感情移入やリベラルな人道意識すら寄せ付けない、そのような〈悲惨〉が、人間の生と死とを、その前にただ立ちすくむしかない何かのごとく抽出していく。そうしてあらゆる装飾が強制的に剥ぎ取られ、剥き出しにされた生と死が、現実を苛酷に更新する。自らの娘の死を「犬か猫の死にぎわ」のようなものとして語るしかない状況とは、そういう事態である。

悲惨
そのような〈悲惨〉は、本書において、たとえば、次のような被害女性の語りをも導き出すこととなる。その女性は、水俣病に罹って入院するなかで、身ごもった赤子を流産してしまう。そうして、「うちは大学病院に入れられとる頃は気ちがいになっとったかも知れん」(157;引用文中の「差別語」は、作品の時代性を鑑みてここではそのまま使用する)という語り出しで、女性はある晩のことを語る。
なんさま外はもう暗うなっとるようじゃった。お膳に、魚の一匹ついてきとったもん。うちゃそんとき流産させなはった後じゃったけん、ひょくっとその魚が、赤子(やや)が死んで還ってきたとおもうた。頭に血の上るちゅうとじゃろ、ほんにああいうときの気持ちというものはおかしかなあ。
(中略)
早う始末せんば、赤子(やや)しゃんがかわいそう。あげんして皿の上にのせられて、うちの血のついとるもんを、かなしかよ。始末してやらにゃ、女ごの恥ばい。
その皿ばとろうと気張るばってん、気張れば痙攣のきつうなるもね。皿と箸がかちかち音たてる。箸が魚ばつつき落とす。ひとりで大騒動の気色じゃった。うちの赤子(やや)がお膳の上から逃げてはってく。
157-158。
そうしてベッドから転げ落ち、痙攣で思うように動かない肉体をよじりながら、「逃ぐるまいぞ、いま食うてくるるけん」(159)と、小皿から落ちた魚を追う女性――本書は、このような有様を、患者自身の語りとして繰り返し示そうとする。それはまた、(ここまでの引用だけでも十分明らかなように)優れて口語的な世界、水俣言葉によって描かれる世界として提示される。言い換えると、口語による表現が、〈悲惨〉を生活世界の具体性のなかに捕捉するのである。それは、本書が随所で文語的なものを、つまりは医者のカルテや行政の議事録を、いわば対位法的に引用することで、さらに強調されることとなる。上記の女性が、痙攣のせいで、「自分の足がいうことをきかずにあっちでもこっちでも馬鹿んごと走り出す」(161)様子を打ち明ければ、その直後に医学雑誌から、水俣病に罹った猫が「踊リヲ踊ッタリ走リマワッタリシテ、ツイニハ海ニトビコンデシマウ」(162)という報告が引用される、という具合である。
孤絶
こうして、沿岸に生きるものたちの生活世界の隅々を刺し貫くものとして〈悲惨〉が現れるとき、人間も、人間以外の生物も、ともに自らの〈自然〉を喪失せざるをえない。言い換えると、そこでいかに生や死が剥き出しのものとして現れざるをえなかったとしても、そこでの〈剥き出し〉であるということは、もはや自然であることを意味しない。剥き出しであることが非日常な事柄であるばかりでなく、そうやって剥き出しになったもの自体もまた不自然でしかありえないという、二重の否定形において表現される事態がここに現れている。自然(nature;本性)は、ここで破壊的歴史性によって徹底的に侵食される。かつて、自然と歴史という凝固した対立図式を克服しようと哲学者たちが試みてきた努力は、驚くべき邪悪さでもって貫徹されることとなる。
そのような事態に投げ出されるということは、そのものたちにいかなる性質を与えることになるのか?――本書が描き出したものを一言にするならば、〈孤絶〉である。たとえば、上述の女性は、「心ぼそか。世の中から一人引き離されてゆきよるごたる。うちゃ寂しゅうして、どげん寂しかか、あんたにゃわかるみゃ」(151)と、世間の理解も期待できない場所に自らを感得する。また別のある少年は、病院に行くことを頑なに拒絶する。通院を促す声に対して、彼は、「いやばい、殺さるるもね」(31)と答える。本書が描くように、この言葉には著しく「切迫」したものがある。世間――いや、世界は、彼にとってもはや自身を閉じるべき〈敵〉としてしか感覚されない。このような〈孤絶〉は、この少年においてほど深刻ではなかったとしても、バスで病院へと通う子どもの水俣病被害者たちの、どこか明るさのある表情にすら見受けられる。
ひとりで何年も寝ころがされている子たちのまなざしは、どのように思惟的な眸よりもさらに透視的であり、十歳そこそこの生活感情の中で孤独、孤絶こそもっとも深く培われたのであり、だからこそこの子たちがバスに乗り、その貌が一途に家の外の空にむけてかがやくとしても不思議ではなかった。
24。
自己内対話を可能性として留める孤独とは区別して孤立があるのだとすれば、その孤立がそれでもなお持っていた世界への信頼までもが失われてしまう事態が〈孤絶〉である。孤立においてすでに世界との繋がりは失われてしまっているけれども、それでもなお自らにとって外在的なものとして志向されうる世界が、〈孤絶〉においては一切の信頼を失ってしまい、敵対的なものとして現出することになる。この孤独から〈孤絶〉にいたるまでの暗いグラデーションのどこかに、彼らは投げ出されている。そこでは、青い空や光輝く海といった外的自然の見せる美しい光景のみが、最後の信頼を保つのである。
想起
こうして、世界から〈孤絶〉してしまっているという状況は、現在の世界ではなく、「かつてそうであった世界」、すなわちチッソによって汚染される前の生活世界の想起へと人びとを向かわせる。本書が〈悲惨〉や〈孤絶〉と同時に描くのは、まさにそういった、かつての世界へのいきいきとした想起である。「魚は舟の上で食うとがいちばん、うもうござす」と、重い症状を抱えた孫を育てる老人は答える。「舟にゃこまんか鍋釜のせて、七輪ものせて、茶わんと皿といっちょずつ、味噌も醤油ものせてゆく。そしてあねさん、焼酎びんも忘れずにのせてゆく」(219-220)。そうして漁を終えて帰ろうとしたとき、海がベタ凪ぎで舟を急がすことができなければ、いい風が出るときまで、潮水で米を炊き、山盛りにした刺身をつまんで、焼酎をぐびぐび飲みながら過ごす。これほどの「栄華」があろうかと目を細めて語る老人の、その手元には、もはやそのような生活は返ってこない。

上述した女性にとっても、入院中に一番想い出されたのは、やはり海の上でのことだったという。彼女の人生にとって、夫と過ごした海での生活は、ほとんどすべてと言ってよいほどのものであった。海のなかにも春夏秋冬や美しい名所があったと、彼女は語っている。
海の水も流れよる。ふじ壺じゃの、いそぎんちゃくじゃの、海松じゃの、水のそろそろと流れてゆく先ざきに、いっぱい花をつけてゆれよるるよ。
わけても魚どんがうつくしか。いそぎんちゃくは菊の花の満開のごたる。海松は海の中の崖のとっかかりに、枝ぶりのよかとの段々をつくっとる。ひじきは雪やなぎの花の枝のごとしとる。藻は竹の林のごたる。
海の底の景色も陸の上とおんなじに、春も秋も夏も冬もあっとばい。うちゃ、きっと海の底には龍宮のあるとおもうとる。夢んごてうつくしかもね。海に飽くちゅうこた、決してなかりよった。
167-168。
繰り返しになるが、このような波間の記憶は、すでにそれが失われてしまった事態のなかで想起されているものである。美しさを誇った魚たちも、水銀のヘドロのなかで死屍累々の姿を晒している。女性もまた、きっと自分があの海での生活に戻ることはできないことを悲しく感じとっている。そこでのこのような叙述は、いわば追悼的想起というかたちをとる。本書は、不知火海沿岸に生きる人びとを襲った〈悲惨〉と〈孤絶〉を描き、失われた生活世界における追悼的想起を経由して、かつての波間の記憶を美しさへと純化する(そこに潜むある論点については、のちに本連載にて触れられるだろう)。
この一連の、精神の動線を確認しておきたい。しかもよく知られているような、喪失による想起の促しとしてではなく、本書が描く、危機と想起を結ぶ、この密度において――本書において読み解かれなければならないのは、まさにこの密度である。なぜなら、すでに大事なものを、繰り返し、取り返しがたく喪失してきた私たちの時代、いや、これまで一つまた一つと積み上げられてきた〈取り返しがたさ〉が、たしかに残酷な悲喜劇として実を結びつつある私たちの時代においては、想起するという能力もまた決して安全ではないからだ――その重みは鉛のように増しているにもかかわらず、である。『苦海浄土』という、時には(特に都会者には)畏怖すらも感じさせてきた作品に、そしてその作品を生み出した「石牟礼道子」という名の作家に、私たちが再び会いに行かなければならない理由はここにある。いましばらく、この突然の訪問を記録していきたい。
(続く)