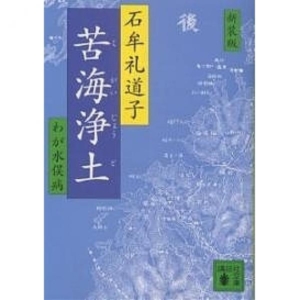「人類初の産業公害」と呼ばれることもある水俣病。それに光を当てた石牟礼道子『苦海浄土』のなかで、共同体における「女」が担う固有の役割とは何だったのか。本作第一部から第三部に丁寧に目配せをした論考をもとに、石牟礼道子の独特なフェミニズムに光を当てる、短期集中連載の第三回。
Written by 井沼香保里&黒岩漠
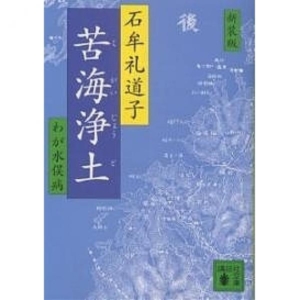
女性
石牟礼道子が女性であり、かつ作家であったということは、彼女の生まれ育った共同体においてどのような意味をもっていたのか? そして、『苦海浄土』において、女性はいかに描かれたのか? この問いへの答えを、テクストの外部(歴史的背景、社会情勢)を丁寧に織り合わせながら、これ以上にない鮮やかさで示している論考が、文学研究者谷口絹枝による「石牟礼道子『苦海浄土』三部作――語り手「わたくし」の母系的位相」(『方位』第30号、熊本近代文学研究会、2013年)だ。
これまで、『苦海浄土』を読む研究者たちの多くは、この作品の特徴的な文体や語りの方法のほか、とりわけ、読み手に鬼気迫る凄みを感じさせずにはおかない「ゆき女きき書き」をはじめとする第一部に目を向けてきた。一方で上記の論文は、第一部から第三部まで通して読むことで初めて明らかとなる石牟礼のフェミニズムに光を当てている。
入院当初、人工流産を施され、そのうえ性愛が壊されて行くゆき女の男女の断絶に対する絶対的な孤絶間、その怨嗟の行き場のない不条理は石牟礼の祖母へつながり、高群〔逸枝〕のいう母系制の転覆以来の母たちの歴史へとつながる。
谷口、14;〔〕内引用者補足。
たとえばこの引用が示すように、石牟礼にとってフェミニズムとは、単に作品の部分を構成しているという以上のもの、まさにこの作品が成立する条件とこの作品が表象するものの在り方を規定する本質的な問題であるということを、谷口は示してみせたのだ。連載第三回となる本記事では、この論考を船頭として、『苦海浄土』という豊穣な海、そこに幽かに開かれた、共同体における女性という航路をたどってみようと思う。
主婦
石牟礼が育った共同体において、日常的なものとは何だったか?――それは、日々の営みの中で女性に不均衡に覆いかぶさる負荷であったという。幼少期、家業の破産とともに、水俣のなかでも下層民の住む部落(俗称とんとん村)に移り住んだ石牟礼は、共同体や家制度がもたらす女たちへの負荷を感受して育った。家庭内では、母親が父親の暴力に耐え、祖母は祖父の妾との同居を余儀なくされ、精神疾患を患った。そして、家の先隣には娼家があった。
こうした生い立ちを経て、1963年、当時36歳だった石牟礼は、一冊の本から、すなわち文明が疎外した生命の根源としての「母性」、それを中心に据えた世界の構築を志向する母性主義を掲げる高群逸枝の『女性の歴史』(1954年)から、「眩暈が起きるほどの衝撃」を受ける(谷口 6)。彼女は、職場と家庭の二重労働に女は爆発寸前であり、そうした爆発寸前の女の情念が歴史を別様に展開させる予兆を読み取る高群の主張に共鳴し、疎外された女性への関心を強めていくのだった。

こうした背景は、石牟礼をして、『苦海浄土』における著者であるところの語り手=「わたくし」を、たんなる個人以上の存在へと位置付けさせることになる。たとえば、この本をめくる指は、突如として現れる次のような言葉とぶつかるだろう。
わたくしの抽象世界であるところの水俣へ、とんとん村へ。抽象の極点である主婦の座へ。
石牟礼道子『苦海浄土』池澤夏樹=個人編集 世界文学全集III-04、河出書房新社、165。
しかし、ここでの「主婦」は、たんに石牟礼自身がそうであった以上に、家制度のなかで疎外される者、すなわち、石牟礼自身がそうありたいと願う「無名の人」のことである。そして「わたくしの抽象世界」とは、近代化の過程で社会から踏みにじられた無名の人たちに生じた心性に関して、「わたくし」が私的に語る魂の世界のことである。無名の人たちが疎外された状況がより明確に浮き上がる位置、すなわち、「水俣」から「とんとん村」へと下降した場所が「わたくし」の表現の立脚点であった。
加えて「わたくし」は、疎外された女、主婦であるのみならず、当時の下層民の共同体の中では例外的な存在である「物書き」でもあった。主婦と物書きという、共同体において二重の違和を抱えた石牟礼の文学は、まさにこの下層の人々が生きる前近代的な「無文字世界」と、近代的文化としての「文字世界」がせめぎあう場で育まれたのだった(谷口 7)。
族母Ⅰ
このようにして、作品のなかで語り手「わたくし」の立ち位置は主婦の座に置かれるのだが、それは踏みにじられた無名の人びと、無力な人びとという位置にあり続けることを意味するのではない。むしろ、そこに力強い〈跳躍〉の契機が用意される。すなわち「わたくし」は、共同体を代表する一種神がかり的な存在「族母」へと徐々に移行していく。
第一部の結び、水俣病で両親を亡くし、病を抱えた弟を介護して結婚をすることのなかった茨木妙子という人物が、ついに来訪したチッソの社長らを見送ったあと、「わたくし」を迎える場面がある。
「ちっとも気が晴れんよ……。今日こそはいおうと、十五年間考え続けたあれこればいおうと、思うとったのに。いえんじゃった。泣かんつもりじゃったのに、泣いてしもうて。あとが出んじゃった。悲しゅうして気が沈む。(中略)親からはおなごに生んでもろうたが、わたしは男になったばい。このごろはもう男ばい。」
伏目になるとき風が来て、ぱらりとほつれ毛がその頬と褐色の頸すじにかかる。その眸のあまりのふかいうつくしさに、わたしくしは息を呑んだ。霧のように雨を含んでひろがる風である。
「そうそ、お下がりば貰いまっしょ。仏さまから」
草いきれのたつ古代の巫女のように、彼女はゆらりと立ち上がる。仏さまのほうにゆき「お供物」を捧げ下ろし、そのまま台所にゆき片手に庖丁をもってあらわれる。
石牟礼『苦海浄土』第一部、191。
その共同体の内部で、もはや主婦でもなく、おなごですらないという妙子をみて、「わたくし」はその出で立ちの美しさに息を呑み、「巫女」と形容している。そして第二部以降、このように霊能がかった存在として表現されるのが「族母」なのだ。こうして第二部の冒頭は、第一部で胎児性患者、江津野杢太郎の面倒を見ていた爺さまが死に、湯の児リハビリ病院に入院した杢太郎を見舞いに来る婆さまに焦点があてられる。
婆さまが面会に来ると、この病室には一種ののどやかな世界が出来上がる(中略)。草履をつっかけて、草道を踏みわけて歩いてゆく足音や、その後姿だけで、ひとつの村の成り立ちから終りまでを、そっくりあらわすような、老媼だけがもつ、おのずからなる権威でもって、婆さまは、部屋にいる間じゅう、子どもたちの心を統帥する。お世辞もお行儀も斟酌もない、直截な心で。(中略)わが孫を含めて、花の盛りどころか、いのちの芽のまま、変形しつつあるものたちを目の前にして、なすすべもない本能者のいかりとやさしさが、彼女をそうさせる。みずからの生もくずれようとするきわの、族母のような無口な寂寥から。
石牟礼『苦海浄土』第二部、208-210。
ちなみに谷口が指摘するように、「族母」という語は、高群が『女性の歴史』において、いのちのつながりを前提とする原始の母性我が創出した母系氏族制の社会の主宰者(たとえば、邪馬台国の卑弥呼、琉球の姫彦制など)を指す語として使われていたものだが、それがこの石牟礼のテクストで顔を出しているのだ。
ここで、谷口の論文のなかで殊更言及されてはいないものの、卑弥呼という形象が敗戦後の日本社会で重要な意味をもっていたことについて、触れておいてもよいだろう。天孫降臨の神話のために古代史が犠牲にされていた戦中までの期間が終わったとき、卑弥呼は、二重の意味で特別な位置を占めることになったのだ。第一に、卑弥呼とは、天皇制以前の日本を想像させるものであった。天皇制以前を想像するということ――それは天皇制無き日本を想像するということでもあって、そのようにして卑弥呼は、一つの可能性としての未来を触発したのである。
第二の点もまた、この点の裏地をなすものである。すなわち、卑弥呼という形象とともに、家父長制ないし男性中心の歴史と社会の外部を想像するということ――これである。天皇制が家父長制と根底において結びついているということは、かつて現在以上に明確に認識されていた問題であった。敗戦直後から始まった女性の社会的・政治的権利を要求する運動は、天皇制と家父長制の外部に、卑弥呼という形象をいわば武器として見出したのである。高群から石牟礼へという思想系譜の後ろで働いていたのも、まさにこのような意味が仮託された概念としての「族母」であっただろう。その輝かしい地位からたんなる歴史教科書の覚えるべき一単語へと、卑弥呼が没落していった現在――そのような現在の位置から再び『苦海浄土』へと、「族母」へと、私たちの舳先をいましばらく向けなければならない。
族母Ⅱ
第二部終章では、胎児性患者の娘たちの母親の一人であるトキノという人物が、桜の花びらのような蝶の夢を見たというエピソードが登場する。桜の花びらのような蝶は、死んだ娘が夢のなかでとった姿である。そのトキノは、夢見の翌日、蝶=死んだ娘の供養のために、「わたくし」にこう語りかける。
「それであなたに、お願いですが、文ばひとつ、チッソの人方に書いて下はりませんでしょうか。いんえ、もうチッソでなくとも、世の人方の、おひとりにでもとどきますなら」。
石牟礼『苦海浄土』第二部、451。
この場面で生じたのは、「水俣の民俗の基層にも宿っていたはずの『族母』の一人である『トキノさん』によって、共同体の女性たちから女性たちへと受け継がれた声を伝える語り部」(谷口17)の役割が、筆者=「わたくし」に託されたということであり、まさにそのことによって、共同体において物書きであることと主婦であることの二重の負荷を背負っていた「わたくし」に、共同体を導く希有な役割が与えられることになるのだ。
こうした過程を経て、第三部では、ついに「わたくし」自身が「族母」となる。その〈跳躍〉がなされるのは、顔の見えない裁判闘争に納得できず、チッソとの直接談判を開始した患者と家族による自主交渉派の動きに焦点が当てられ、「わたくし」も患者たちと行動を共にする場面である。
よいこと、でなくとも人間というものは心楽しく笑うことができるのである。わたくしは一瞬真面目な哲学者のようになり、一族の族母の気持ちにもなり、心はいそがしかった。
石牟礼『苦海浄土』第三部、672。
この石牟礼のテクストを引用して、続けて谷口は次のような注釈を付けている。
患者とその家族、そして寄り集まってきた若者を中心とする支援者たちで創る幻想の地域共同体、その一族の行く末を祈り見守る「族母」の座に自らを位置づけようとする。「族母」の心情にそって、語り部として水俣病を書く「わたくし」の立場を引き受ける事態だといえよう。尊敬する文化人から「役にも立たない」抗議文書よりは、「じっと辛抱して」作品を書くべきだと忠告を受けた「わたくし」が、その言葉が身に応えながらも「ひとは事を為すことへの効果より、ただ人情で、もろに惑乱してしまうこともある」と独りごつ姿は、どこにもない幻想の地域共同体を創造する者の覚悟を伝えている。
谷口、18。
共同体において何重もの違和を抱えた存在であり、かつ自身も無名の人たらんとした石牟礼が、「族母」に連なる女として、なおかつ共同体の運命を文字世界とつなぐ作家として書いたのが『苦海浄土』であったという、この読みは、たんに抑圧された女性のエンパワーメントといった問題系にとどまるものでないことは明らかだ。族母を中心に展開する幻想の共同体は、それがすでに実体を持たないからこそ、いくらか皮肉なことにも、決して近代の資本主義市場経済の論理にからめとられて崩されたり、消え去ったりしてしまうことはない。そこにおいて賭けられているのは、たとえ幻想であっても、霊的であっても、たんなる願いであっても、それでもいのちのつながりを言葉で紡ぎ続けて絶やさない――そういった決意としてのフェミニズムなのだ。