「人類初の産業公害」と呼ばれることもある水俣病。そこには、趨勢ないし力としての近代が問題の根源として伏在していた。チッソは、近代史においていかなる位置を持つのか? 私たちは、いかにして〈近代の夢〉へと抵抗することができるのか? 石牟礼道子の作品から〈覚醒〉の方途を考える、短期集中連載の最終回。
Written by 黒岩漠&井沼香保里
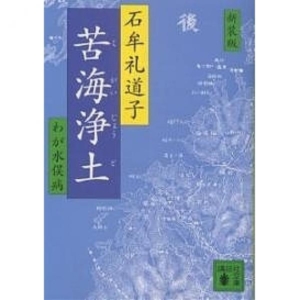
近代
主婦が族母へと〈跳躍〉する――この変身を要請した事態とはいかなるものであったか? その内在的理由は、石牟礼が現実と幻想を連続させるそのやり方においてすでに見たとして、外在的理由は何であったか? それは一言にするならば、近代(modern:現代)というしかないものだ。狩猟採集生活から農耕生活への一大変化を遥かに凌駕するほどの変質を世界に生み出している趨勢ないし力――近代という語でまず了解されなければならないのは、時代としてより以前に、そのような趨勢ないし力である。呪術や族母といった概念へと向かう石牟礼道子の思想の運動もまた、このような意味での近代への抵抗であったと言ってよい。しかし、世界史の各所で発見される次の命題が忘れられないかぎりは、である。すなわち、近代が古代を引用する。この世界史の各所に見出される命題がここでも妥当するのだ。
近代国家の、資本主義の、近代の産物としての天皇制の、家父長制の、それらの外部に向かおうという彼女が依拠するイメージは、古代というよりむしろ原始社会に属するものであるが、その〈引用〉の身振りにおいてほかと違いはない。つまり、彼女の抵抗もまた一つの近代、一つの趨勢ないし力なのである(近代における〈引用〉のあり方については、以下の関連記事も参考になる)。明治維新へといたる古代王政「復古」のパトスと、族母へといたらんとする石牟礼のパトスとが形式的に類似するのもそのためである。したがって問題の所在は、ともに近代の内部で理解しうる、ある種の力とそれに抵抗するまた別の力との布置関係にある。そのためまず把握されなければならないのは、水俣病とチッソ(新日本窒素肥料株式会社;現在はチッソ株式会社として水俣病の補償業務専業)が近代において持つ歴史的位置であろう。

チッソ
チッソが日本の近代史において持つ位置は、実はいくつかの意味において象徴的なものである。一つに、企業としての歴史的展開過程において、チッソは、ある一定の段階に達した資本主義経済の典型として、財閥および帝国主義の中心に位置する点が挙げられる。1906年、のちの大企業家・野口遵(のぐち・したがう;1873年-1944年)は、鹿児島県北部で水力発電所を運営する曾木電気を設立する。この会社がチッソを中心とした財閥の一つ、いわゆる「日窒コンツェルン」へと展開していくということ、またチッソばかりか、現在の旭化成、信越化学、積水化学、積水ハウスといった大企業の前身ともなるということは、実業家列伝の類いが記憶しているとおりである。
そしてもう一つ認識されなければならないのは、この財閥が植民地・朝鮮で果たした役割だ。野口が半島に進出し、朝鮮総督府の後ろ盾のもと各所に水力発電所を造り、朝鮮窒素やホテルなどを設立した過程もまた、近代が帝国主義という形態においてとる典型の一つである。敗戦後、GHQによる財閥解体をあらゆる抜け道を用いて切り抜けたあと、各財閥は自身の「復興」を企図していく。植民地からの撤退で資産の大半を失った「日窒コンツェルン」もまた、手元に残った水俣工場をまじまじと見つめたことだろう。

チッソは、水俣の人びとがそれを自身にとって「必要」なものだと考え続け、また欲し続けたという点において、なお一層、近代の象徴の座へと奉られることになる。知られているとおりチッソは、敗戦後の経済成長を支える企業の一つとして、水俣に展開していった。市の税収の半分をチッソが占め、市街地面積の四分の一を関連用地とした時期もあり、市内には数多の社員が住んだ。水俣で「会社」といえば、ただチッソのことこそを指す。
近代は、水俣に対していわば〈取引〉を持ちかけたと言ってもよい。欲望や「必要」が歴史的変数である以上、豊かさとは幸福ではなく、力であり、また力への夢である。近代は、チッソを媒介に、日本に化学肥料を与え、水俣に経済的繁栄を与え、市内の人びとに豊かさの夢を与え、不知火に工場排水を、漁村に水銀被害を与えた。それは、貧困からの脱却を求めた日本の地方都市――工場を呼び込んで公害に苦しんだ数々の地域ばかりでなく、軍港を招致して原子爆弾の投下対象となった広島、原子力発電所の建設を受け入れ、あの大災害によって放射能がばら撒かれた福島などと、事柄の本質において共通の問題圏に属する。この点において、チッソとその帰結としての水俣病は、魅力あふれる力としての近代、それが持ち出す危険な取引の結末を象徴する位置を占めるのだ。
近代の夢は犠牲を強い、続いて犠牲者たちに沈黙を強いる。『苦海浄土』を含むあらゆるテクストが書き留めているように、補償を求める患者たちに対して、「会社がなくなれば水俣はどうなる」、「患者たちは金欲しさに自分のことしか考えていない」といった言葉が水俣市民によって吐かれた事実は、彼らにおいて、夢がすでに覚醒を待つ状態ではなく、日々彼らが生きる現実の生そのものかのごとく凝固してしまっている状態を示している。重要なことにも、近代においては、「仕方がない」ことのリストは際限なく増えていく。何かを「仕方がない」と他者に思わせること、「仕方がない」のかけ声のもとで他者を沈黙させることは、力そのものの作用である。その力に抗おうとすれば、即座に敵として認識される。生へと擬態した近代の夢に生きる人びとは、ひとたび生活が不安定化する可能性が見えれば、共犯者以外のあらゆる他者に先取り的に敵のイメージを押し付ける。敵の手による自身の死が鋭敏に予感されるのだ。生となった夢が待つのは、もはや覚醒ではなく、ただ死のみである。この来るべき死こそが、取引の先に待ち受ける物語の終末なのである。そして物語は、死の不安を侍らせつつ、いまだ終わらない。

覚醒
族母への〈跳躍〉を目指し、アニミズムとプレアニミズムを標榜し、患者たちの語らぬ言葉を語り、徹底的に〈悲惨〉を描き、追悼的想起によって喪われた「美しき不知火」を幻視する、それら石牟礼の方法のすべてを要請したのは水俣の近代であり、そうした近代への抵抗方法を与えたものもまた近代として見出しうるのだとしたら、そこで近代が歴史的構造体という意味での〈時代〉として貫徹した――それと裏表の関係にあるのは、言うまでもなく近代の破壊的歴史性による漁民の生活の犠牲化と喪失である――ことを驚く前に、認識しなければならないことがある。すなわち、内部衝突する二つの力の癒着と乖離である。
それは、ここまでに用いた語にしたがうのなら、夢という癒着点、そして死と覚醒という乖離点として表現されるだろう。チッソが水俣に見せた豊かさの夢は、水俣病の発生を軸に時間のベクトルを逆向けにすれば、喪われた過去に豊かさを見出すという、石牟礼の見せる夢(ないし幻想)と切り離しがたく結びつく。「死霊や生霊の言葉を階級の言語と心得ている」必要が、つまりは進歩を目指すマルクス主義の言語に死霊や生霊の言葉を結びつける必要が石牟礼にあったのは、まさにこの癒着に起因するのである(『苦海浄土 わが水俣病(新装版)』講談社文庫、2004年、75、また本連載《2》も参照)。
しかし、チッソの夢が自らを白昼の世界の中心に位置づけ、人びとにとって生そのものであるかのように偽装し、そうして死の気配を与えながら忌避させるのに対して、石牟礼の夢は、書物という暗がりの世界で〈悲惨〉を凝視し、詩的に在りし日の想起を促すことで、覚醒へと向けて夢を深めるのである。覚醒――チッソの、近代の見せる夢からの、そして石牟礼自身の夢もまた…。
本連載《1》で考察した患者たちの〈孤絶〉とは、ここでの文脈に沿って再定義するならば、近代の夢からはじき出される事態として理解することもできるかもしれない。そこでは、夢が悪夢へと転じるのではない。もはや夢が共有されなくなるのだ。だとすると、人びとがあらゆる近代の夢から覚醒するということは、彼らにおいては投げ出された〈孤絶〉状態からの解放を意味するだろう。それは、たとえ『苦海浄土』において苦海と浄土が結合されたとしても、そこですでに達成されているわけではない。夢は、いまだ覚醒へいたるほど深まってはいないのだ。そのかぎりにおいて、たとえすべての水俣病患者が世を去ったとしても、彼らの〈孤絶〉が癒されることはなく、また世界の外部に新たな〈孤絶〉と〈悲惨〉が生まれ続けるだろう。であるからこそ、私たちは、繰り返し石牟礼のもとを訪問し続け、また彼女の仕事を新鮮に受け取りなおす必要があるのだ。
苦海浄土
本連載がここまで考察してきた『苦海浄土』という書物と石牟礼道子という書き手について、もしたんに「近代への抵抗」という手垢にまみれたフレーズに要約して記憶してしまうのだとしたら、すべては無価値なものに貶められるだろう。その場合の問題は、そのような要約で分かったつもりになる私たち読者の側にある。記憶されるべき内容も、記憶する側が見合った能力を持っていなければ価値を維持できないのだ。重要なことは、そのようなパラフレーズではなく、個々の具体的な細部にある。個々の具体的な記述、個々の状況に対する具体的な対応、そのなかで練り上げられていった方法――そこから離れてしまうことなく、にもかかわらず、そことは別の状況で、記憶を確保し、また活用すること。のちに生きる者たちに求められるのは、常にそのような精神である。
石牟礼道子という存在を具体的なものとして記憶するには、本連載のように彼女に内在的な諸要素の連関を考察するだけでなく、彼女とは異なる方法態度と比較するという手もある。水俣病という状況だけにかぎっても、本連載でもわずかに触れた緒方正人やユージン・スミス。あるいは石牟礼に影響を与え、またともに九州で活動した森崎和江や中村きい子。レンズをとおして水俣病患者を見つめた桑原史成。また最も患者たちに触れ続けた医者・原田正純。石牟礼の文筆生活を支え、また追悼的認識の方法を独自に追及した渡辺京二。そして石牟礼が不知火をあたかも桃源郷のように描いたことを批判し、石牟礼とは異なるかたちで鋭く「原点」を追及した谷川雁…。これらの思想家・物書きは、それぞれのやり方で諸々の「苦海」を見つめ、またそれを「浄土」へと転化する方法を模索したのではなかったか?
記憶されるべきものは、過酷な世界の状況の波間にいくつも浮かんでは消えていく。私たちは、その一つひとつを見逃さないように、この世界に目を向け続けなければならない。その注視は、私たち自身がこの世界、あるいは近代について、忘れがたい疑問を抱いているときにこそよく為しうるのではないだろうか? すなわち、近代への進歩を素朴に信じるのでもなく、近代によって壊されていったかつての世界を美化してみせるのではなく、「近代にもそれ以前にもそれぞれの困難があったのだ」などと語ってみせることで、平らにならされ、薄められた歴史感覚に停滞するのでもない、そのような近代への問いの姿勢はどのように可能なのか――この問いこそが、私たちに記憶することを促すのではないだろうか?
(完)




