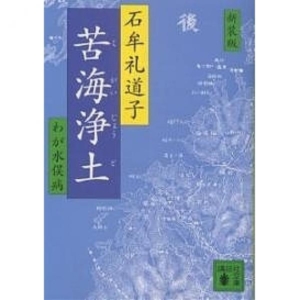ジャック・デリダの講義録『獣と主権者』。政治的なものをめぐって、デリダが考え、語る教室を多くの動物たちの形象が通り過ぎて行く。そのなかでも特段目立つ動物――〈狼〉。本記事は、デリダが〈狼〉をめぐって繰り広げる政治的なものについての声に対して、遠くからの応答を響かせる。前編。
Written by 黒岩漠
流れ着いた瓶のなかの〈獣〉
ジャック・デリダ〔1930-2004年〕の講義録が相次いで邦訳・出版されている。白水社から「ジャック・デリダ講義録」として出版されているこれらのシリーズは、晩年の死刑をめぐる政治哲学的思考から1960年代のハイデッガー読解にまで及ぶが、そのしばしば奇妙な話運び、意表を突く問いの出し方からは、まるでデリダという思索者の息遣いが聞こえてくるようだ。主著として知られる作品群への補論という枠には収まらない、貴重な記録であろう。一気に読んでしまうことはおすすめしない。内容を要約的に整理することなど、なおさらおすすめしない。たっぷり時間を使って読んで、デリダが一瞬触れて過ぎていった問題群、あるいはむしろ彼の講義室をサッと通り過ぎていった言葉や形象を逃がさず捕まえて、大事に取っておくような読み方をする方がよい。デリダについて能弁に語ることができるほど彼の仕事の熱心な読者ではない僕にも、そのことはすぐに察せられた。
ここに邦訳された講義録の一つがある。『獣と主権者Ⅰ』(西山雄二・郷原佳以・亀井大輔・佐藤朋子訳、白水社、2014年;のち2016年にⅡも邦訳・出版)。2001年から2003年まで、2年連続で行われたデリダの最終講義の前半である。〈獣〉と〈主権者〉――政治的なものをめぐる思想史の、ある意味では決定的な局面に現れる〈獣〉たちの表象。動物(animal)というよりも、獣(bête)という語においてこそ問題化されるべき問いの範疇は、政治的なものの領域を逆なでに読み解いていく端緒となる。〈獣〉なるものを想像し、同時にそれを排除しながら、それと自らを対置することによって成立するような〈主権者〉の概念を、デリダは、多様な動物たち――狼や狐や蛇や羊や鷲といった多様な動物たちを招くことによって揺り動かそうとする。
本記事は、この講義録に対する精緻な読解ではない。彼とはまるで異なる場所を生きる僕が、いわばどこか違う島から届いたボトルメールを、いささか戸惑いながらも受け取って、その余白に僕の生きる島の事情を書き込んだ――そのような代物が本記事である。特に〈狼〉、デリダの語りのなかに、何度も、というより複数登場する、意味上の相貌を異にする狼たち。その群れに向けて、僕の位置からいくらかの「追記」を行いたい。少なくとも表面的には系譜の異なる数頭の狼が、かの群れとどのような関係を持ちうるのか。それらは政治的なものといかなる関係を持ちうるのか。少しでも考えられたらよいと思っている。
狼の方へ
La…le、このフランス語の冠詞に書き込まれた性差から、デリダの問いははじまる。獣と主権者(La bête et le souverain)。獣は女性名詞で、主権者は男性名詞ということだ。「La bête et le souverain」。あるいはそこに、決定的な「s」を忍び込ませて、一足飛びに「獣とは主権者である(La bête est le souverain)」という命題を引き出してしまってもよいだろうか? 獣が主権者? そのような命題がなぜ成り立つのか? それともそのような命題は、やはり「bête !(馬鹿だ!)」と言われざるをえないのだろうか? いや、むしろ〈主権者〉は、自らが思い描く反対物によって、すなわち〈獣〉的な要素によって構成されているのであることが、ここで示されるべきなのだろうか? デリダは言う、「すぐにそのことを示そう」と。

しかし、何を? まぁ「すぐにそのことを示そう」。彼は、「忍び足で=狼の歩みで(à pas de loup)」で、狼の方へと近づいていく。
最強者の理屈はつねに最良のものである。
すぐにそのことを示そう。
この一言から寓話は始まる。
一匹の小ヒツジが、喉の渇きを癒した、
綺麗な水の流れの中で。
一匹の狼が、お腹をすかせて突然姿を現す。偶然の出来事を求め、
空腹のために、この場所に引き寄せられたのだった。
誰がお前をそんなに大胆にし、俺の飲み物を濁らせるんだ?
と、その動物が怒りに燃えて言う。
お前は向こう見ずな行為の罰を受けることになるぞ。
お殿様、と子羊が応える。陛下が
お怒りになりませんように。
むしろ、ご理解ください、
私が渇きを癒した
水の流れは、
陛下がいらっしゃるところよりも20歩以上に下にあります。
ですから、どのようにしても、
陛下のお飲み物を濁らせることはできないのです。
お前は濁らせている、と残忍な野獣が言う。
わしは知っているぞ、去年、お前はわしを悪く言ったではないか。
どうして私にそんなことができましょう、まだ生まれていませんでした、
と子羊。私は今もまだ母の乳を吸っているところです。
もしお前でなければ、お前の兄だ。
兄はいません。だったらお前の家族の誰かだ。
なぜというに、わしに対して情け容赦ないではないか、
お前たちも、羊飼いも、犬たちも。
わしに言ったものがいる。復讐しなければならない、と。
そう言うと、森の奥に、
狼は子羊を運び、食べてしまった。
どんな形の裁判もなしで。
※以上の邦訳は、以下のサイトに掲載されたものを利用した。大変素晴らしい解説とともに紹介されているので、ぜひ読んでいただきたい。

以上は、ラ・フォンテーヌの寓話「狼と子羊」の全文である。ラ・フォンテーヌは、横暴な狼と哀れな子羊を召喚するのだ、強い者の理屈(raison;理性、理由)が最良であるとされる事情をここに示そうと――そう、「すぐにそのことを示そう」、これはラ・フォンテーヌの言葉であった。しかし、デリダは、この寓話を引いておきながら、しかも講義のなかで繰り返し引いておきながら、まだ提示のための手続きを続けようとする。先人を真似てすぐにそのことを示すと宣言しながら、いまだそれは示されていないこととして振る舞い続ける。最良たる強者の理屈、その提示は(ラ・フォンテーヌの意図とは真逆なことにも)いつまでも遅延させられる――。
この遅延は、彼の講義室にさらなる狼たちが集まるのに十分な余裕を与えるだろう。古代ローマの喜劇作家プラウトゥスに由来する「人間は人間に対して狼」であるという言葉、それを引用しながら〈各人の各人に対する戦争状態〉としての自然状態を説明するホッブズの政治理論、ラ・フォンテーヌやホッブズと同時代に生きたパスカルの正義と力についての断章…。理性や政治に対置されながら獣性、〈法の外〉に置かれる獣性を背負わされてきた、ヨーロッパ政治思想史上の比喩の〈狼〉が、既知の二項区分を揺るがせていく。
(後半に続く)