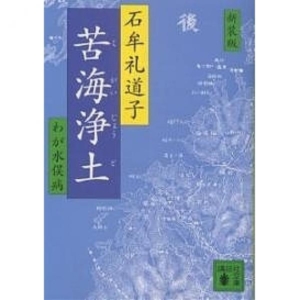五十嵐大介による漫画『海獣の子供』には、物語の合間に「海に纏わる証言」がいくつも挿入されている。こうした挿話がもつ役割とはなにか?民俗学における民話や伝承、そして近代科学の限界に挑戦した19世紀末の知の営みにも言及しながら、この作品における証言の機能に迫る!
Written by 井沼香保里
技法としての証言
「現実」を逸脱する事象や対象について語るとき、人はどのような手段に頼るだろうか。その主だった、そして代表的な手段はフィクションとしての文学だろう。既知の自然法則や科学的な推論からは否定されるような事象や存在は、想像された世界のなかであれば十全に語られる資格を得る。一方で、もしフィクションではない方法で語るとしたら、それは「証言」という体裁をとることだろう。「私は幽霊を見た」とか、「私の友人には超能力があり未来を知ることができる」とか、直接話法で提示される、言葉による証として。
五十嵐大介による漫画『海獣の子供』(2007年~2012年、全5巻)には、この証言という手法が、フィクションの物語世界の真実らしさを担保する一つの仕掛けとして、ちりばめられている。
たとえば「海に纏わる第一の証言」は、次のように描写される。
初夏の満月の夜、水中カメラマンが海の中で珊瑚の産卵を撮影するため海に潜っている。暗い海の中に卵が無限に漂い、まるで星のような光景が広がるなか、彼は、二人の赤ん坊を目撃する。そしてこの描写の次のページをめくると、男性がこちらに向かって「海には魔物がいる。」と語る。そして次のコマで、「元・水中カメラマン、K・B・ソデス氏の証言、フィリピン・クヘブ島で収集。」というナレーションが入る(五十嵐大介『海獣の子供』第1巻、13―18頁)。

読者はここまで見て/読んではじめて、先ほどの海中の光景はこの男性の語りであり、過去の回想であったことを知る。絵を通じて、彼の経験が読者に直接手渡されるのだ。
もちろんこうした方法は、必ずしも『海獣の子供』に特徴的なものではなく、真実味を醸し出すために一般的に使われるテクニックである。しかし、この方法がこの作品において用いられるとき、それは、この物語自体の中核的なメッセージを運ぶ不可欠な容器として有効に機能しているように思えてならない。
私は以前の記事で、この作品の物語が中心人物を持たないまま、「誕生祭」という、海と宇宙が繋がり星々が生まれる特別な瞬間に向けて展開していき、〈人間の休止〉を表現していく様子について書いた。

今回は、この「誕生祭」をめぐる壮大なメッセージを、証言という技法がどのように支え、展開していくのかを見ていこう。
「海に纏わる証言」の真実らしさ
作品の中には、前述の第一の証言と同様のスタイルで、全部で10の証言が挿入されている。これらがこの物語の合間には唐突に入ってくるのだが、どれも脈絡がないわけではない。たとえば、この物語の主要な登場人物である、ジュゴンに育てられ海中で生活してきた海(うみ)と空(そら)という少年たちの境遇は、この第一の証言が初めに入ることによって、読者にとっては既知のものとなる。現実にはありえない話だが、すでに聞いたことがある、知っている情報となるのだ。
加えて、それを語る人物に固有名詞が与えられ、収集した場所まで書かれていると、読者は少しだけ騙されもするかもしれない。さすがにこの物語全体はフィクションだとしても、ここに挿入されている証言くらいは、ひょっとしたら、実在するのではないかと。
ちなみに、10の証言が収集されたという場所は、上述したフィリピンの「クヘブ島」のほか、第二の証言のオーストラリアの「ケイクコート」、第三の証言のアメリカ「サウス・フィッシャーマンズワーフ」、第六の証言のフランス「ナルロー」、第七の証言の日本の「江ノ倉」というように、どれも非常に「ありそう」な架空の地名である。国名は知っていてもその国の個々の島や地名までは熟知していないであろう多くの読者にとって、これらの証言は、想像された物語世界のなかに不意に入り込んでくる現実味のある逸話として、想像と現実の境界を揺るがしながら、読者を物語世界の中に引き込む装置として機能しているといえるかもしれない。
民話や伝承との違い
こうした「現実離れ」した類の話が豊富に見いだされる分野は、なににおいても民俗学だろう。
民俗学では、たとえば岩手県遠野の伝承を集めて記録した柳田国男の『遠野物語』であったり、アイルランドに伝わる妖精や幽霊に関する逸話を集めた詩人ウィリアム・バトラー・イエイツの『ケルト妖精物語』であったりと、現実としては考えられないような超自然的な民話や伝承が数多く記録されてきた。
しかし、その多くは語り部によって語られるものや、その地域に長い間伝わる民話であって、重要なのはその真実らしさよりも、語られた内容の豊かさや特殊性のほうだといえよう。たとえばイエイツが、こうした伝承を集めて公表することによって、大英帝国の支配に抵抗するアイルランド固有のナショナリズムを喚起しようとしたように。
こうした民俗学的な叙述に対して、『海獣の子供』のなかで挿入される数々の証言のありかたは少々異質だ。これらはたとえ架空であったとしてもどこか特定の場所に縛られるものではなく、偏在的で、かつそれを体験した当事者によって直接的に語られるという形態をとる。このことによって、そこで起きたとされる出来事と読者との間の距離は、局所的で、語り部を通じて提示される民話や伝承よりもずっと近くなる。加えて、そこでの記憶が語りだけでなくイメージとしても共有されることで、読者も一緒にそれを追体験しているような感覚を憶えることができるのだ。
心霊研究における確信
こうした証言と読者との間の近さは、むしろ、19世紀後半にイギリスを中心に発展した心霊研究がたどり着いた方法と重なり合う。
ケンブリッジ大学に在籍していた教授陣を中心に1882年に設立された英国心霊研究協会は、テレパシーや幽霊の目撃談などを検証していたが、彼らは統計や実験における確率論を用いる一方で、精力的に証言の収集をおこなっていた。哲学者アンリ・ベルクソンは、1913年に同協会の会長に就任した際、こうした証言の収集という手法は、数学的な確実性も物理学的な確実性ももたらさないために、科学者らの反感を買っていると指摘した。
しかしベルクソンは、そうであるからといって、この手法そのものの可能性を否定しない。彼は、士官である夫が戦死した瞬間の光景を遠く離れた場所で見たと主張する女性の証言を例にあげながら、彼女の「具体的でありありとした光景の叙述」を、真実か誤りかという抽象的な次元で判断しようとすることの誤りを指摘する。そしてさらにこう述べる。
もしその場面に登場している彼女の知らない兵士の顔が現実のとおり彼女に現れたということが確信さえできるならば、そのときにはたとえ誤ったまぼろしが幾千あったと証明され、彼女の見たもの以外に本当の幻視が決してなかったとしても、私はテレパシーの実在が厳密かつ決定的に立証されたものと考えます。
『精神のエネルギー』平凡社、2017年、108頁、下線部は筆者による。
ここでの「確信」の必要条件をベルクソンは明示していない。しかし、こうした具体的な経験の叙述は、彼がこのあとで述べるところの近代科学、すなわち「経験の領域を縮小」し、計量可能な方向のみを考慮する科学の動向と相いれないものであることは明らかだ。ここで求められていることは、あらゆる証言を集めて多くの虚偽を暴き、確率的にその類の証言を一括して否定することではない。そうではなく、ありありとした光景を語る証言のたった一つでも、わたしたちが、「そうだ」と確信できるかどうかが問題なのだ。
知の限界に挑む、現実味
このように考えてみると、『海獣の子供』に挿入された10の証言という語りの技法は、まさに「誕生祭」という〈人間の休止〉に向かっていくなかでこの作品が繰り返し説く、既存の科学的な知や、人間を中心とした認識枠組みの限界というテーマを補完するものとして捉えることができるだろう。
たとえば作中で、鯨特有のコミュニケーション能力から、高度な知の体系を作り上げている可能性を指し、鯨を「特別な存在」と考える海洋学者ジムらに対し、「海のなんでも屋」を自称する伝統航海術師であり呪術師でもあるデデはこう反論する。
それは鯨の能力がたまたま人間にも理解しやすい形で、人間と比べやすいだけだろ。
しょせん人間が特別な存在だって考え方の上に立ってるのさ。
人間には理解できない
そこにある事に気づく事すらできない秩序や価値や知があるかもしれないんだから。
『海獣の子供』第3巻202頁。
また、主人公・琉花(るか)の母親で、対人コミュニケーションを苦手とし、アル中の酒浸り生活をしている加奈子は、海女の家系に生まれ、自らも海女として海に潜っていた過去を持つ。彼女が、誕生祭に巻き込まれて行方不明となった琉花を探すためにデデと船で海上に出た際の以下のセリフも印象的である。
……イルカも……
波も……雲も……
わたしの目に見えるほとんどは
人間じゃない。
世界の大部分は“人間じゃないもの”でできてるでしょう?
だからわたしは人間じゃないもののほうを多く見る。
でもどうやらそれはダメらしい……
世界を割合の通りに見てるだけなのに、
どうやら他の人たちは違うらしい…
『海獣の子供』第4巻87-88頁。

このようにして示される人間の認識の限界や、そうした認識に基づいて発展してきた科学を万能視することへの批判的な視座は、再現性のない一回限りの「ありありとした光景」として現実味をもつ証言が随所で挿入されることによって補完される。これらが生き生きと語られて描かれることを通して、近代科学が保証する現実では到底受け入れることのできないような出来事が、少しずつ、しかしラディカルに、読者にとっての現実を侵犯していく。
メタレベルでの「不可能な」証言
この物語において提示されている証言は、しかし、唐突かつ断片的な10の挿話にとどまらない。あまりにも壮大な物語が展開していくためにうっかり忘れそうになるが、そもそもこの物語は、孫と船に乗る琉花が「海のはなしをしよう」と切り出し、「私が体験した事、調べた事、聞いた事…私だけが知っている…海の物語を……」と語るところから始まっている。10の証言は、琉花が調べたり聞いたりしたものであり、そしてそれらを包摂するが物語全体もまた、彼女が自身の過去の体験を回想した証言という体裁をとっているのだ。このことは、作者である五十嵐が、証言という技法をこの物語を補完する装飾的なものにとどめおくのではなく、まさにこの物語自体を運ぶ船として、意識的に用いていたことの証左ではないだろうか。

一方でこのようなスタートを切っておきながら、物語は次第に、一登場人物としての琉花が知りえないような、他の登場人物たち同士の会話や彼らの過去の回想にも踏み込んで展開されていく。物語はいわば全知の語り手を必要としており、琉花個人の回想や認識の範囲を超えていくのだ。
この意味で、10の証言を包摂するメタレベルの「証言」として提示される本作品は、挿入された個々の証言とは明らかに異なる位相において展開されている。琉花という一個人の認識を入口としながらも、物語が展開していくにつれて、気づけば身体や時間の制約を課された一人の人間には認識不可能な領野が開けていくのだ。
こうして『海獣の子供』は、その語り/描きの技法においても人間を超えている。したがってここにおける証言は、誕生祭という〈人間の休止〉を伝えるためのこれ以上にない技法であると同時に、このメッセージそのものでもある、とはいえないだろうか。